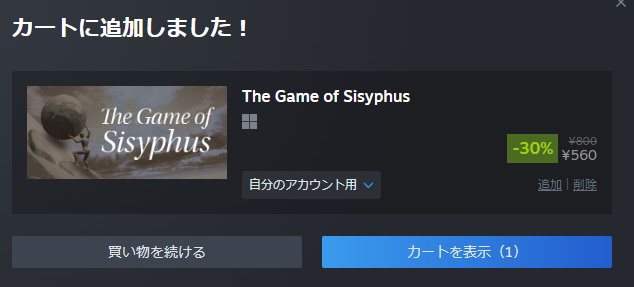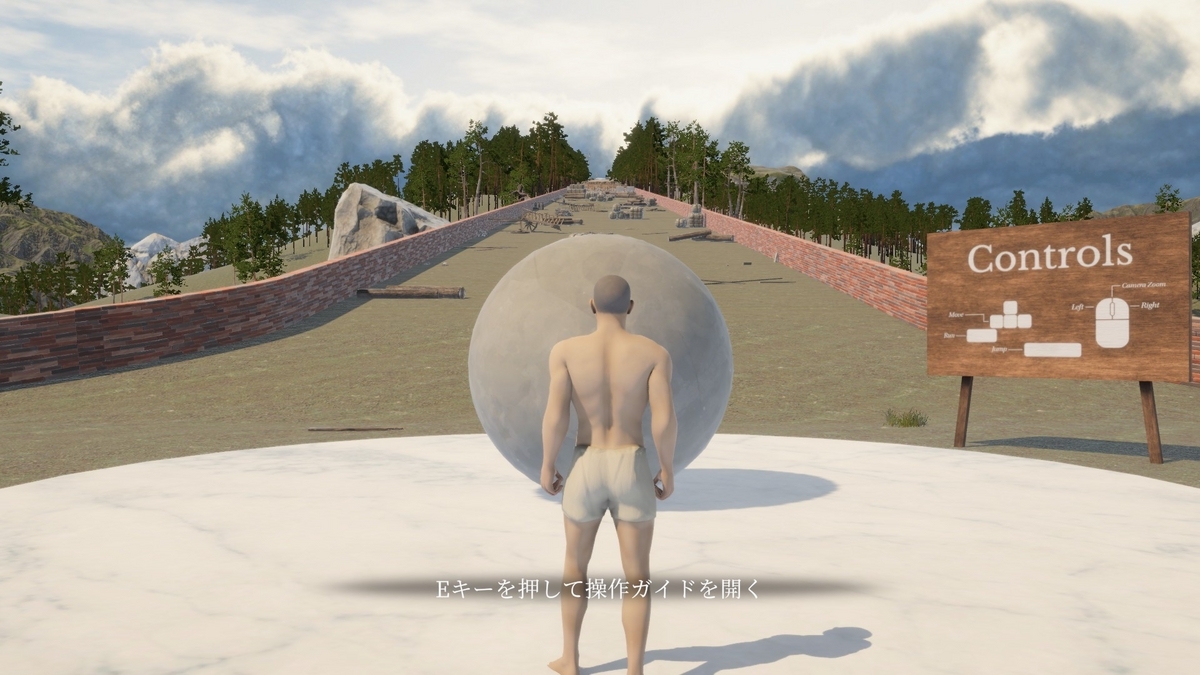【2024.04.23追記:ここから】
本記事の公開後、下記増田の作者様から直接ご連絡を頂戴し、動画の作成および公開について快く承諾をいただけた。この場を借りて改めて御礼を申し上げるとともに、折角なのでということで再録・編集した動画を下記のとおり動画を公開する。まことにありがとうございました。インターネットにも感謝します。
【2024.04.23追記:ここまで】
いつものようにはてなブックマークを見ていると、あるはてな匿名ダイアリーの記事に出会った。
面白い! 落語みたいでいいですね。と感じた矢先、これは声に出して読むとより面白いのではないか、と思った。早速読み上げてみると、やっぱり面白い。面白い話は演る側にとっても面白いのである。興奮冷めやらぬ中、私にしては珍しく、今すぐに形にしなければと、腹の底から意欲が湧き出て、とりあえずPC上で録音してみた。読みやすいように、適宜関西弁にアレンジし、3,4テイク重ねてみると、これは面白い! と感じられるものができあがった。
ようしせっかくなので動画にするかと、いらすとやから桜餅の画像をダウンロードし、録った音声と組み合わせることにした。深夜1時のことである。明日も朝から仕事であるのに、一体何をやっているのか分からないが、抑えきれない創作意欲がそこにはあった。

うおおおおお!!! と未だに慣れない手付きで作業を行う。タイトルはどうしよう。ストレートに『桜餅』でもいいが、『道明寺』としたほうがそれっぽい。そうだそうだそうしよう。『道明寺』。なるほど響きが良いのではないか。こうして溢れんばかりの熱意によって、一つの動画が生まれたのである。

と言いつつ、このあたりで少し冷静になってきたのか、できあがった動画を見ると、音量とかリズムとか滑舌など、もっとより良くできそうな気がしたが、こういうものは勢いも大切である。面白いと思ったものを、面白いと思えているうちに作り終えるのが大切ではないだろうか。そう自分で自分に演説をかましながら、満足気に視聴を続けていたら、次に私の頭によぎったのは、ある種当然の思考だった。この動画をYoutubeにアップしよう。面白いと思ってくれる人がきっといるだろう。何より作ったままPC上に眠らせて置くのももったいない。そうだそうだと脳内議会で野次が飛ぶ。よしじゃあこの勢いのままネットの海に放流してしまうか~とYoutubeスタジオを開いた時、頭にアラートが鳴り響いた。私はこの動画をYoutubeにアップしてもよいのだろうか?
ニコニコ動画に入り浸っていたあの頃であれば、何も考えずに「これ面白いから見て~」と無邪気にやっていたであろう。しかし、今は違うのだ。もうだいぶ歳を取ってしまった私の脳裏に浮かんだのは、「著作権」の3文字だった。
状況を整理しよう。すなわち、私が行った・行おうとした行為は次のようにまとめられる。
①はてな匿名ダイアリーに投稿された桜餅に関する記事(以下、「本件増田」という)を
②関西弁風にアレンジして
③読み上げて録音し
④画像と組み合わせて
⑤『道明寺』と銘打った上で
⑥Youtube上に投稿する。
このような行為を、本件増田の投稿者から許諾等を得ることなく行うのは、著作権法上許容されるのか。結論としてはダメと思われる。以下、検討する。なお、筆者は著作権法の専門家ではないので正確性は保証されない。
⓪当該文章は著作物であるか
一般的に文章は、言語の著作物として保護され(法第10条1項1号)、それはインターネット上で書かれたものでも変わらない。事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道はその例外となるが(同条2項)、本件増田がそれに該当するとは考えにくい。
①はてな匿名ダイアリーに投稿された内容の著作権は誰に帰属するか
投稿内容の著作権は投稿者に帰属することが、ヘルプ上に明記されている。
したがって、②~⑦の行為が、本件増田の投稿者に帰属する著作権法上の権利を侵害するか否かが問題となる。
②関西弁風にアレンジするのは許容されるか
真っ先に思い至ったのは翻案権であるが、何が翻案にあたるかはファジーである。とりあえず条文を見てみよう。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
いつ見てもよく分からない条文であるが、翻案に当たるかどうかでその先の検討に違いが生じてくる。本来は判例等を参照しながら検討する内容であるが、お恥ずかしながら手元にコンメンタールはおろか文献らしい文献がないので、ただただ考えてみよう。
後述の③とも関連するが、単純に書かれた文章を読み上げるだけであれば口述権(第24条)の話が、そしてその音声を録音するとなると複製権(第21条)の話が出てくる。この点、複製というのがいわゆるデッドコピーを想定し、文章そのままに読み上げる行為が該当するのだとすると(第2条1項15号)、少なくとも方言で読み替える行為は複製とは言えないように思われる。
ただ、例えばもともと東京が舞台である物語を大阪に置き換えました、となれば分かりやすく翻案であるが、ただただ共通語あるいは東京弁を関西弁になおした場合はどうか。この点、自分で演じた身からすると、方言が変わることで、語り手のキャラクタ性もが変わったものになっているように思われる。コテコテの関西のおっちゃんが喋っているのか、大阪生まれだがそろそろ東京で暮らした時間の方が長くなってきたおっちゃんが喋っているのかで、創作物が持つ物語性も変わってくるのではないか。そう考えると、やはり翻案に傾くように思われる。あるいは、シンプルに翻訳と同じように考えればよいのかもしれない(ただし、別の言語に訳しているわけではないのでその定義に当てはめられるかは疑義がある。)。
当該行為が翻案になると捉えた場合でも、私的利用の範疇であれば著作権の行使は制限される(47条の6第1項1号)。したがって、私が家で一人楽しむ分には問題ない。しかし、Youtubeにアップロードして、そのリンクをブログ上で公開した場合、アップロードという行為はもとより、当ブログにはアドセンス広告が貼られていることも踏まえると、私的利用とはみなされないだろう(Youtubeチャンネル上に広告設定をしている場合も同様であろう)。
③読み上げて録音するのは許容されるか
上記②で述べたとおり、投稿された文章をそのまま読み上げて録音する行為は、著作権法上の複製に該当する(第2条1項15号)が、私的複製と捉えられる場合には複製権の行使は制限される(第30条1項)。この点の議論は②と変わらない。
そして、本件においては先に翻案の有無が問題となるところ、②において翻案であると解されるのであれば、反対に複製権の観点では問題とならない。
④画像と組み合わせるのは許容されるか
概ね上記②で行った議論のとおりであり、結果的には、本件増田をアレンジしてさらに画像と組み合わせるということになるから、やはり翻案の性質が強くなるのではないか。
なお、いらすとやにおいて、素材の画像を動画に用いることは、商用・非商用を問わず一つの動画あたり20点以下の利用に収まる限りで認められている。
⑤『道明寺』と銘打つのは許容されるか
もともと本件増田のタイトルは『関東地方で桜餅を騙っている簀巻き野郎について』であり、これを変えることは、上記②のとおり翻案のほか、同一性保持権も問題になるだろう(第20条第1項)。同一性保持権は、いわゆる著作者人格権の一つであり、一応一定の権利制限規定が存在するが(同条2項)、本件においてはそれらに該当しない。
同一性保持権は、翻案権とは別概念のため、私的利用による例外は適用されず、観念的には私が『道明寺』との名付けを行った時点で、投稿者の同一性保持権を侵害しうることとなるのではないか。
この点、著作者がタイトルの変更も含めて翻案を許諾しているような場合には、同一性保持権の不行使にも同意しているとの推定が働くと思われるところ、同様に、私的利用により翻案権の行使が制限される場面においては、同一性保持権の行使も制限されるとの整理ができないか。結論として、財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権を同種のものと捉えるのは適切でなく、そのような整理は難しいと考える。すなわち、各種の権利制限規定は、著作権者と利用者の利害を調整するため例外的に設けられているものであり、その効力をいたずらに著作者人格権にまで広げるべきではなく、またそのように広げられる合理的理由も見いだせない。
⑥Youtube上に投稿するのは許容されるか
上記②④⑤により、本件動画は本件増田の翻案により制作されたものと解される。すなわち、本件増田の投稿者は本件動画の原著作者となり、二次的著作物の著作権者たる私と同様の権利を行使できることとなる。
また、Youtube上への投稿は、自動公衆送信(2条1項9号の4)または送信可能化(同9号の5)に該当する。そしてこれらの行為には著作者への許諾を要する(第23項1項)。
したがって、私は作成した動画をアップロードする権利を有するが、それは原著作者たる本件増田の投稿者も同様である(第28条)。加えて、②に関連して言えば、そもそも最終的に公衆送信を目的としている時点で、やはり私的利用による翻案とは解されないだろう。
以上より、私が本件動画をYoutubeでアップロードし公開するためには、本件増田の投稿者から翻案及び公衆送信に係る許諾ならびに同一性保持権の不行使に係る同意を取得する必要がある。